泥遊びは、保育園において夏の定番遊びです。多くの保育園でやっているようですが、親からは洗濯が大変、衛生的にどうなのか、など様々な理由からやめてという声もあったり?!でも、泥遊びをするねらいもちゃんとあるようです。
我が子の保育園も、毎年6月頃から泥遊びが始まります。私個人的には、家でそのような遊びは一緒にやってあげられないので、保育園で大いにそんな遊びをやってくれるのは、良いのかなって思っています。泥遊びのねらいとか考えたこともなかったため、今回いろいろ調べてみてなるほど~と思うことがたくさんありました。ここに、まとめてみますね!!
水遊びに関することもこちらの投稿でまとめています!!
泥遊びの4つのねらい
泥遊びは、子どもが泥の感覚を楽しむこと、そして想像力を養い、子どもたちが友達と豊かなコミュニケーションを図っていくことをねらいとしています。
五感を刺激する
泥遊びをすることで、子どもの五感の発達を養うことができます。泥は、砂と水の配分によってその形や手触りが変わります。自分たちでいろんな泥をつくり触れることで、触感が刺激されます。手だけでなく、泥の上を裸足で歩き足の裏からもいろんな感触を感じることができます。
好奇心旺盛な子どもにとっては、毎日同じ泥遊びをしているようでも毎日違う感覚を味わっています。
想像力が養われる
泥遊びでは、お団子を作ったりと泥でいろんな造形をして遊びます。しかし、割れたり崩れたり、思ったようにいかないこともあります。
そんなときに、「どうしてうまくいかないのかな?」「どうしたら良いのかな?」という想像をして、保育士が「こうやったらどうなるかな?」「今度はここをこうしたらどうかな?」というように、子どもが創意工夫できる手助けをすることで、子どもは自発的に工夫をするようになります。
自然に興味を持つ
砂も水も自然界のものであり、泥遊びを通して、その先にある自然全体に対して子どもが興味を持つようになります。保育士が、その時子どもが抱く疑問を一緒に考え、発見した喜びを共感し、褒めてあげることでさらに自然に興味をもち、泥遊びも楽しくなります。
社会性が身につく
泥遊びを通して、友達とのコミュニケーションの取り方を学ぶことができます。友達と一緒になっ何か作ろうとしたときには、友達と対話をしながら役割分担をし、道具を譲り合ったりして、完成した時には友達と一緒に達成感を喜びで感じます。
泥団子の作り方
みなさんは子どもの頃には泥団子を作ったことがありますか?
泥団子作り、楽しかったですか?
きっと、泥団子作りは楽しく多くの方が子どもの頃に経験をしてきており、そして今も子どもたちは大好きです!!
では、ここで、泥団子の作り方を調べてみたのでまとめます。
泥団子は、固めの泥と仕上げ用のサラサラの砂で作ります。
水分が多すぎると固まらないため、砂に少しずつ水を足し、握り固められる粘度になるよう、微調整をしていきます。
泥が団子状になったら、仕上げにサラサラの砂でコーティングをします。
これで完成です!!
ぜひ、泥団子の作り方を忘れてしまったという方は、参考にして、子どもが「泥団子作ろう!!」と言ったら、一緒に作ってみるのも良いと思います!!
親が心配している服装はどうする?
我が子の保育園の場合ですが、泥遊びシーズンになると、汚れても良い服装で登園してくださいと案内が来ます。そして、毎日着替え一式とビニール袋を鞄に用意してくださいと案内があります。
泥遊びは、朝着ていった格好そのままで、裸足になって園庭で遊ぶようです。そして、肌着まで濡れ汚れるが前提です。
・・・汚れても良い服って??
初めて聞いた時、そんな服ないけどな・・・というのが第一に思ったことで、服どうしよう・・・と思いました。
お下がりとかたくさん服を持っている方はそんなふうに心配に思わないかもしれませんが、特に長子の場合は私と同じように思う方もいるのではないのでしょうか。
そこで、私はどうしたかと言うと、安いものを泥遊び専用に買い揃えました。我が子の保育園はこのシーズンには毎日泥遊びをやるので、毎日の替え用も必要になります。なので、上下3着ずつ、1着300円代のお安いものを買いました。
そのシーズンで着たおす覚悟で買っていますが、意外にもサイズさえ間に合えば翌年も着ることができます。
ぜひ、服装に迷ったり困ったりしていたら、お安い服はあるので、古着でなくても安い新品を泥遊び専用に用意するのもありだと思います。
泥で汚れると、洗濯しても落ちませんので、泥遊び専用に服は用意しておくべきでしょう。
まとめ
保育園でする泥遊びのねらいは4つ!
以上のねらいから、子どもにとって泥遊びは遊びを通して様々な成長を促します。準備や片付けに親は多少の負担がありますが、子どもの成長を願いやっていきたいものです。
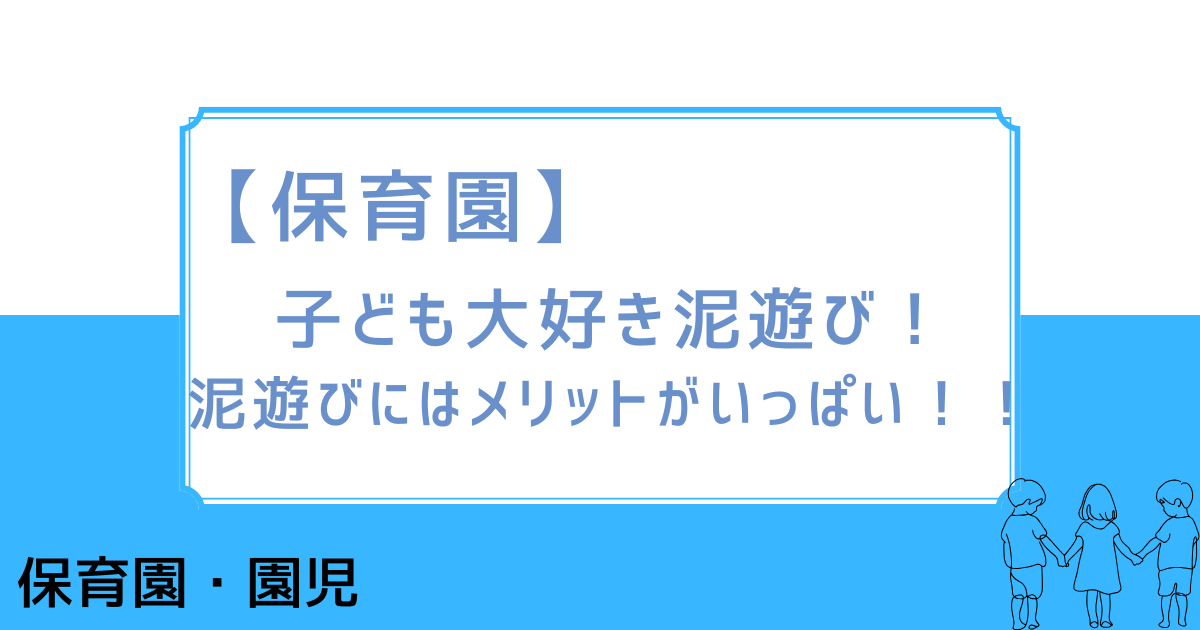
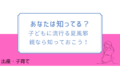
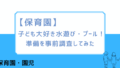
コメント