小学生の夏休み、1か月以上もの長い期間、子どもは休みでも親は休みではない家庭が多いでしょう。共働きの家庭も多く、毎日1日中家で子どもだけで過ごすことができないお子さんもいるでしょう。そんな現代の小学生の夏休みの過ごし方にはどんなものがあるか、調べたのでまとめます。まだ悩んでいたり困っていたりするご家庭は、少しでも参考になれば良いなと思います。
夏休みの過ごし方6選!
読書習慣を取り入れる
読書が苦手な子、普段読書する習慣がない子も、夏休みの期間だけでも少し読書に挑戦する機会を作るのはどうでしょうか?
読書が好きで、日頃から読書をする習慣のある子どもは、「夏休みの期間で何冊読書する」など目標を立てて読書に取り組むのも良いと思います。
また、夏休みの課題にある読書感想文に同時に取り組むのありだと思います。まだ読書感想文に慣れていない低学年のうちは、親のサポートが必要になりますが、本を読んで何かを感じそれを自分の言葉で文章にまとめるというのは、子どもの感性を育み語彙力を成長させます。また文章能力も向上します。
苦手な子が多い読書感想文ではあると思いますが、我が子にはぜひ毎年取り組んでもらいたいと思っています。
自然に触れる
普段なかなか外に出て自然と触れ合う時間が作れない子どもも、夏休みは自然と触れ合う絶好の機会です。夏は、植物は元気に咲き乱れ昆虫などは活発に活動しています。
近くの公園で虫探しも良いし、キャンプなどで少し遠出や親の田舎に帰省して川辺で水遊びも良いでしょう。
夏の定番と言えばセミやカブトムシ!捕まえた昆虫の生体を調べるなど、同時に夏休みの自由課題にすることもできます。
最近は子どももスマホやゲームといったデジタルと付き合う時間が長くなってきており、夏休みの長期休みはその時間がさらに増えると予想できます。そこを意識的に外に出て自然と触れ合う時間を作ることで、五感が磨かれ感性が育ちます。
近年は熱中症の危険があるため、日中の気温のピーク時間を避け、朝晩の少しでも涼しい時間帯に自然遊びをすることをおすすめします。
お菓子作りや料理に挑戦する
自然遊びも大事にしたいですが、近年の猛暑日続きではさすがに日中は外へ出ることが危険です。そんな外に出られない日中は、親と一緒にお菓子作りや料理に挑戦するのも良いでしょう。
親は普段忙しくて時間が作れないと、なかなか子どもにお菓子作りや料理を一緒にする機会をつくることができないと思います。子どもの新しい挑戦として、夏休みの自由課題にすることもできるでしょう。
子どもの成長に合わせて少しずつ料理を覚えてもらい、キッチンの使い方も教えれば、家事の担い手として成長し親は助かります。また子どもの将来の自活のためにも、少しずつ経験を通して様々なことを教えていきたいところです。
ボランティア活動に参加する
ボランティアは子どもの社会性や思いやりを育てる貴重な体験ができます。どんなボランティア活動があるのかは自ら見つけないといけないかもしれませんが、自治体の広報や学校から配布されるものに書かれていることがあります。親も一緒に意識的に捜してみて、子どもに提案してみるのも良いでしょう。
地域の清掃活動、夏祭りの手伝い、高齢者や障害者施設との交流、などより身近な地域でボランティア活動ができると、地域のことを知るきっかけにもなります。
イベントやワークショップに参加する
夏休みは、いろんな所で子ども向けのイベントやワークショップが催されています。学校からも広告をもらってきていないでしょうか?
普段やらないこと、経験したことのないこと、1人ではできないこと、家では経験できないことなど、指導者や講師がいるイベントやワークショップで経験、挑戦できるというのは良い機会ではないでしょうか。
親子で参加できるものあるので、ぜひ子ども自身が興味をもったことは親も一緒に参加してみてはどうでしょうか。自由研究にもおすすめです。
家族旅行!!
最後は、家族旅行です。夏休みと言っても親は長期休みがとれないご家庭もあるかと思います。1日でも2日でも、普段行かない所、行ったことのない所へ家族で旅行に行けたら、子どもの思い出になることは間違いなしです。
子どもにどこへ行きたいか、何がしたいか聞いてあげて、子どもと旅行の計画を立てると良いかもしれません。準備から楽しくなりそうです。
子どもの成長に合わせて、旅行先も変わっていくと思うので、親は子どもの成長を感じられるかもしれませんね。
共働き家庭の子どもの過ごし方3選!
共働きの家庭、かつ核家族が主流の現代、親世代が子どものも頃とは夏休みの過ごし方は随分と違うと思います。自分が子どもの頃と今の子供たちも同じように夏休みを過ごせるとは思えません。
また、小学生低学年はまだ一日家で一人では過ごせません。食事はどうするのか問題、一人では日常生活のタイムスケジュール管理はできません。何より、子ども自身「寂しさ」が溢れとてもじゃないけど毎日一人では過ごせません。
では、共働き家庭の小学生は、夏休みの長期休暇どのように過ごしたら良いのでしょうか?どのような過ごし方の選択肢があるのでしょうか?3つ紹介したいと思います。
学童保育、トワイライトを利用する
小学生低学年(小1~小3)のうちは、学童保育やトワイライトを利用するという選択をする家庭が多いのではないでしょうか。小学校入学と同時にこれらの利用申し込みをしており1学期から利用しているお子さんは、そのまま夏休みは朝から1日利用するケースがほとんどだと思います。
学童保育とトワイライトの違いは多少ありますが、1日のスケジュール管理をしていただけるので、家にいてだらだらと毎日を過ごしてしまう、ということを回避できます。学習の時間、読書の時間、遊びの時間、などとメリハリのあるスケジュールで1日過ごすことができます。
子どもも友達と遊べるし、普段は交流の少ない他学年の子とも関われるので、毎日家にいるより刺激のある日々を過ごせると思います。
夏は暑すぎてなかなか屋外に遊びに行くわけにもいかないので、本当にこういう場は親にとってありがたいばかりです。
しかし、学童保育やトワイライトも、小学生高学年(小4~)以降は子ども自身が行きたがらなくなることもあります。そういうお子さんは、そろそろ一人で1日お留守番ということになるのかもしれません。
小学生高学年を目安に、ご飯の支度や1日のスケジュール管理を子ども自身ができるようにしておくことは必要なのかもしれません。
我が子も今年が3年生、今年の夏休みは毎日一日トワイライトの予定です。来年以降本人が何て言いだすか、もしものことも想定して準備はしていく心構えでいます。
実家に預ける
両親の実家が頼れる距離、頼れる存在であれば、実家に預けるという家庭もあると思います。しかし、近年は小学生の親の親、まだ働いている方も少なくないのではないでしょうか?
また夏休みはそれなりに宿題や課題も出ます。それらを見てくれる人がいないと、親が休みの日だけで宿題を管理するのは、結構ハードになります。実家に預ける予定であれば、宿題も見てくれるか、協力を依頼するのも大事だと思います。
親が長期休暇をとる
これはなかなか現実的ではないと思いますが、長期と言っても、夏休みのうちのどこか1週間でも休みがとれると良いのではないかと思います。
というのも、前述した学童保育やトワイライトは、夏季休暇期間ずっと開放されているとも限りません。お盆の期間だけ閉所という所もあるのではないでしょうか?
その閉所の期間のみ実家に預けるというのもありかもしれませんが、子どもは夏休みなのに親は毎日仕事でほとんど一緒に過ごせないのであれば、そのお盆の期間だけでも一緒に休み、夏休みの思い出作りや宿題を集中的に見るのもありだと思います。
我が家は夏休み、こう過ごす!!
小学3年生の男の子と年中女の子がいる我が家の今年の夏休みの過ごし方を簡単に紹介します!!
小学3年生は私が仕事の平日は毎日9時~トワイライトへ行ってもらいます。そこで、学習、読書、遊びとメリハリのある生活を習慣化して過ごしてもらいます。
閉所時間の18時までいるというのであれば、親が迎えに行くまでトワイライトで過ごしてもらいますが、早く帰りたいと言われれば、3年生は17時までなら迎えなしで一人で帰宅することができるので、鍵を持たせ早く帰らせます。
その時は、親が帰宅するまでは外出しない、誰か来客があってもインターホンには出ない、というルールを徹底させます。
そして、お盆の期間はトワイライトが閉所になるので、そこに合わせて私は連休をもらいます。(シフト制なので、全て有休でなくてもどこかで休みを調整することが可能です)
保育園はやっていますが、夏季保育期間と言われ、親が仕事でなければ自宅で保育お願いしますというスタイルなので、年中女の子も一緒に保育園はお休みさせます。
この一緒に過ごせるお盆期間を有効に、宿題の大詰めと思い出作りを計画立てます。私の実家には子どもたちのいとこが集まるので行きたいのも山々ですが、私にとってはこの期間しか集中して子どもたちと過ごせないので、実家は我慢して計画を立てていきます。
このような感じで夏休みの計画立てていますが、夏休みも子どもにとっては成長できる機会です。小3の息子も来年以降はトワイライトへ行ってくれるか分かりません。行かないと言った場合、またこれまでと違う夏休みの過ごし方を考えなければいけません。
宿題やメリハリのある生活を送ることも大切ですが、子どもが少しでも自立できるよう、この機会にできることを増やしたり経験させたりもたくさんしたいと思っています。
まとめ
小学生の夏休みの過ごし方おすすめ6選は、
- 読書習慣を取り入れる
- 自然に触れる
- お菓子作りや料理に挑戦する
- ボランティア活動に参加する
- イベントやワークショップに参加する
- 家族旅行
共働き家庭の子どもの過ごし方3選は、
- 学童保育やトワイライトを利用する
- 実家に預ける
- 親が長期休暇をとる
もう間もなく始まる小学生の夏休み。ぜひ参考に過ごし方の計画を立ててみてください!!
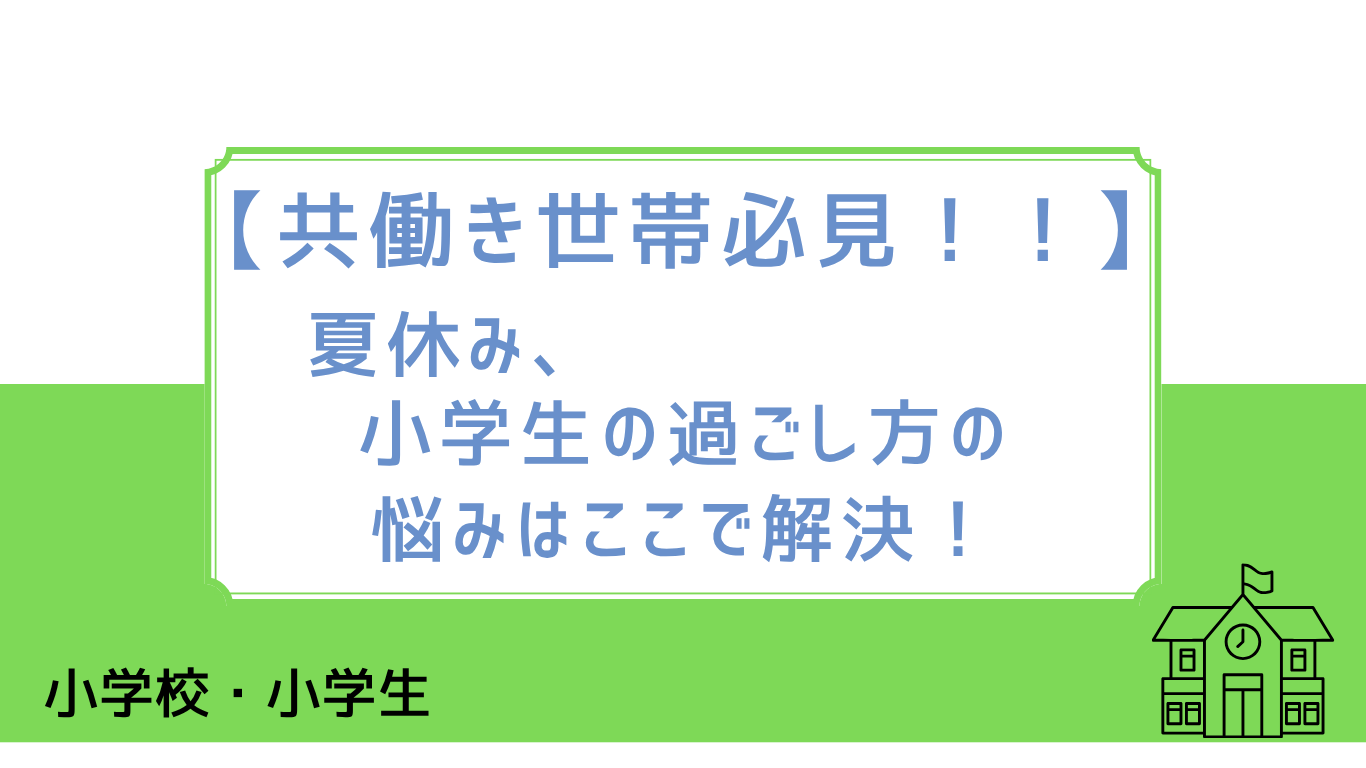
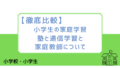
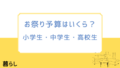
コメント